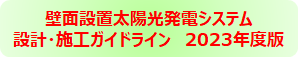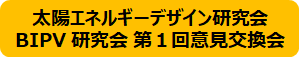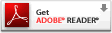2024年度 日本太陽エネルギー学会「若手研究発表会」のお知らせ
・開催日: 2024年7月31日(水)
・会 場: Zoom会議室を利用したオンライン開催
日本太陽エネルギー学会では、再生可能エネルギーに関わる研究に取り組む若手の方々を対象に、今後の研究を進める上で参考になる有益なディスカッション(質疑応答)の場として、「若手研究発表会」を開催いたします。纏まった研究成果だけでなく、発展途上の研究内容も歓迎いたします。優れた発表には「若手研究発表会奨励賞」の贈呈を行いますので、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。
日本太陽エネルギー学会学会活性化委員会
・論文発表資格
主催団体の会員に限らず、どなたでも発表可能です。発表は1人1件に限りませんが、発表論文の採否は日本太陽エネルギー学会に一任ください。
尚「若手研究発表会奨励賞」の受賞は、会員であることが条件になります。
・スケジュール
発表申込期限 7月10日(水)
お申し込みはこちら
またはこちらの申込書に記入いただき事務局(info@jses-solar.jp)まで送付してください。
発表可否通知 7月17日(水)
発表資料提出 7月24日(水)
パワーポイントなど、発表時の投映資料のpdfファイルを提出してください。提出いただいたpdfファイルは、参加申し込みをされた方のみが当学会のサーバーよりダウンロードできるようにします。
発表会 7月31日(水)
※ 発表1件あたり20分程度(発表8分+質疑応答12分程度)。
・参加費
会 員 無料
非会員 3,000 円
※当日までに銀行振り込みにてお支払いください。振込先は事務局より連絡します。
・発表申込み、その他問い合わせ先
一般社団法人日本太陽エネルギー学会 事務局
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-44-14
電話:03-3376-6015 FAX:03-3376-6720, E-mail:info@jses-solar.jp