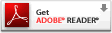□ 戦略的創造研究推進事業(CREST・さきがけ・ACT-X)
■ 2025年度研究提案の募集開始
●募集趣旨
JST戦略的創造研究推進事業「CREST」「さきがけ」「ACT-X」において、2025年度の研究提案募集を開始いたしました。ご関心のある多くの方々のご応募をお待ちしております。
2025年度の募集領域は、2023年度、2024年度に発足した研究領域と2025年度に発足する新規研究領域が対象となります。
また、各研究領域の募集説明会をオンラインセミナー形式(Zoomウェビナー形式)にて開催いたします。
詳細につきましては、募集要項および研究提案募集ホームページをご覧ください。
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
●募集締切
さきがけ・ACT-X : 2025年5月27日(火)正午 厳守
CREST : 2025年6月 3日(火)正午 厳守
募集締切までにe-Radを通じた応募手続きが完了していない研究提案については、いかなる理由があっても審査の対象とはいたしません。余裕を持って、早めにご提出をいただくようお願いいたします。
●研究提案を募集する研究領域
〔CREST〕
◇「ゆらぎの導入・制御による機能性材料の創製」(研究総括:佐々木 高義)
◇「実環境知能システムを実現する基礎理論と基盤技術の創出」(研究総括:尾形 哲也)
◇「人とAIの共生・協働社会を実現する学際的システム基盤の創出」(研究総括:和泉 潔)
◇「異分野融合による超生体組織の創製と新機能の創出」(研究総括:秋吉 一成)
◇「予測・制御のための数理科学的基盤の創出」※(研究総括:小谷 元子)
◇「光と情報・通信・センシング・材料の融合フロンティア」(研究総括:中野 義昭)
◇「材料創製および循環プロセスの革新的融合基盤技術の創出とその学理構築」(研究総括:岡部 朋永)
◇「革新的な計測・解析技術による生命力の解明」(研究総括:水島 昇)
◇「量子・古典の異分野融合による共創型フロンティアの開拓」(研究総括:井元 信之)
◇「海洋とCO2の関係性解明から拓く海のポテンシャル」(研究総括:伊藤 進一)
◇「ナノ物質を用いた半導体デバイス構造の活用基盤技術」※(研究総括:齋藤 理一郎)
◇「細胞操作」(研究総括:宮脇 敦史)
〔さきがけ〕
◇「量子物質」(研究総括:齊藤 英治)
◇「ゆらぎの理解と制御による材料革新」(研究総括:常行 真司)
◇「実世界知能システムの基盤創出」(研究総括:原田 達也)
◇「人とAIの共生・協働社会を構成する要素研究と基盤技術の創出」(研究総括:山下 直美)
◇「多細胞動態の理解と制御による超生体組織の創出」(研究総括:永樂 元次)
◇「AI・ロボットによる研究開発プロセス革新のための基盤構築と実践活用」(研究総括:竹内 一郎)
◇「未来を予測し制御するための数理を活用した新しい科学の探索」(研究総括:荒井 迅)
◇「光でつなぐ情報と物理の融合分野の開拓」(研究総括:川西 哲也)
◇「材料の創製および循環に関する基礎学理の構築と基盤技術の開発」(研究総括:北川 進)
◇「時空間マルチスケール計測に基づく生物の復元あるいは多様化を実現する機構の解明」(研究総括:上村 匡)
◇「量子・古典の異分野融合による共創型フロンティアの開拓」(研究総括:井元 信之)
◇「海洋バイオスフィア・気候の相互作用解明と炭素循環操舵」(研究総括:神田 穣太)
◇「新原理デバイス創成のためのナノマテリアル」(研究総括:岩佐 義宏)
◇「社会課題を解決する人間中心インタラクションの創出」(研究総括:葛岡 英明)
◇「計測・解析プロセス革新のための基盤の構築」(研究総括:田中 功)
〔ACT-X〕
◇「生体機能の理解とデザイン」(研究総括:伊川 正人)
◇「生命と情報」(研究総括:杉田 有治)
◇「AI共生社会を拓くサイバーインフラストラクチャ」(研究総括:下條 真司)
◇「次世代AIを築く数理・情報科学の革新」(研究総括:原 隆浩)
◇「トランススケールな理解で切り拓く革新的マテリアル」(研究総括:竹内 正之)
※CREST-ANR共同提案を募集する研究領域
以下の研究領域では、日仏共同研究グループによる共同研究提案も募集しています。
〔CREST〕
◇「ナノ物質を用いた半導体デバイス構造の活用基盤技術」(研究総括:齋藤 理一郎)
◇「予測・制御のための数理科学的基盤の創出」(研究総括:小谷 元子)
●研究提案募集ホームページ(随時更新)とX(旧Twitter)について
募集要項のダウンロード、各研究領域の募集説明会や面接選考日に関する情報の掲載など、最新情報を発信しています。応募をお考えの方はぜひご覧ください。
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
また、このウェブサイトでお知らせする情報の一部は、戦略的創造研究推進事業のX(旧Twitter)にも掲載します。
https://x.com/JST_Kisokenkyu
●研究提案募集に関する問合せ先
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略研究推進部
[募集専用]E-mail:rp-info@jst.go.jp

 表紙デザインを一新した学会誌
表紙デザインを一新した学会誌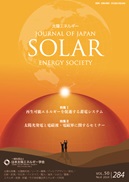 学会誌
学会誌